目の前にある、助けなければならない命のために
地域医療振興協会 女川町地域医療センター今野 友貴

離島地域のみなさんに必要とされる医療に貢献する 崎原永作先生のストーリー
このページに掲載されている情報は2017年10月10日取材当時のものです
地域医療振興協会
沖縄総局 理事・センター長
1984年より自治医科大学卒業医師の義務として沖縄県の離島診療所に勤務(多良間診療所2年半、渡嘉敷診療所3年)義務終了後は県立中部病院の離島支援室として離島支援し、2001年から3年間沖縄県庁の医務課に勤務し医療行政に従事。2004年から公益社団法人地域医療振興協会に入職し、東京北社会保険病院に3年間勤務後、2007年に沖縄地域医療支援センターを立ち上げ、沖縄県からへき地医療支援機構を受託し、専任担当官として離島支援を行っている。
私は沖縄の与那国島出身の両親のもとで6人兄弟の三男として沖縄本島で育ちました。
幼い頃から医師である父親の姿をみていましたから、私も医師になるのだろうと漠然と考えていました。
しかし当時の沖縄県には医学部がありません。医師になるためには沖縄県外の大学に進学しなければならなかったのです。どこの大学に行こうか…進路に悩みましたが、離島出身ということもあり、「将来は医師のいない地域で活躍するのも良いな」と考えていたので、自治医科大学へ進学しました。
自治医科大学に入学すると、私は全国から集まってきた優秀な学生たちに圧倒されてしまいました。
しかし、学長をはじめ、周りの方々に支えていただきながら充実した学生生活を送ることができたと思います。
大学卒業後は故郷の沖縄県へ。自治医科大学の卒業生には自分の出身地に戻り、都道府県庁の職員として地域医療に従事するという義務があるからです。そこで沖縄県庁を訪れた私は、とんでもないことを告げられます。
「崎原くん、ボリビアって知ってるか?」
私は沖縄県内の地域へ派遣されるものだと思っていましたので、この言葉に非常に驚いてしまい、
「ボリビア…南米のボリビアですか?」
と答えるのが精一杯でした。
詳しく話を聞くと、ボリビアには沖縄からの移民が500名ほど集まるコロニーがあり、医師がいないので困っているということでした。
突然のボリビア行きの打診に、大学時代にお世話になった方たちの顔が思い浮かび、気づいたときには
「私は自治医大の医師です。知事の命ずる所はどこへでも行きます!」
と返事をしていました。
結論からいうと私はボリビアに行くことはありませんでした。私が沖縄県内で2年間研修をしている間に、別の医師が着任されたそうで、ボリビア行きの話はなくなってしまったのです。
しかし、あのとき「行きません!」と答えなくてよかったなと今でも思っています。確かにボリビアに行くというのは想定外でしたが、「医師のいない地域ならどんな場所へでも行く」という自治医科大学の覚悟を試されたようなできごとでした。
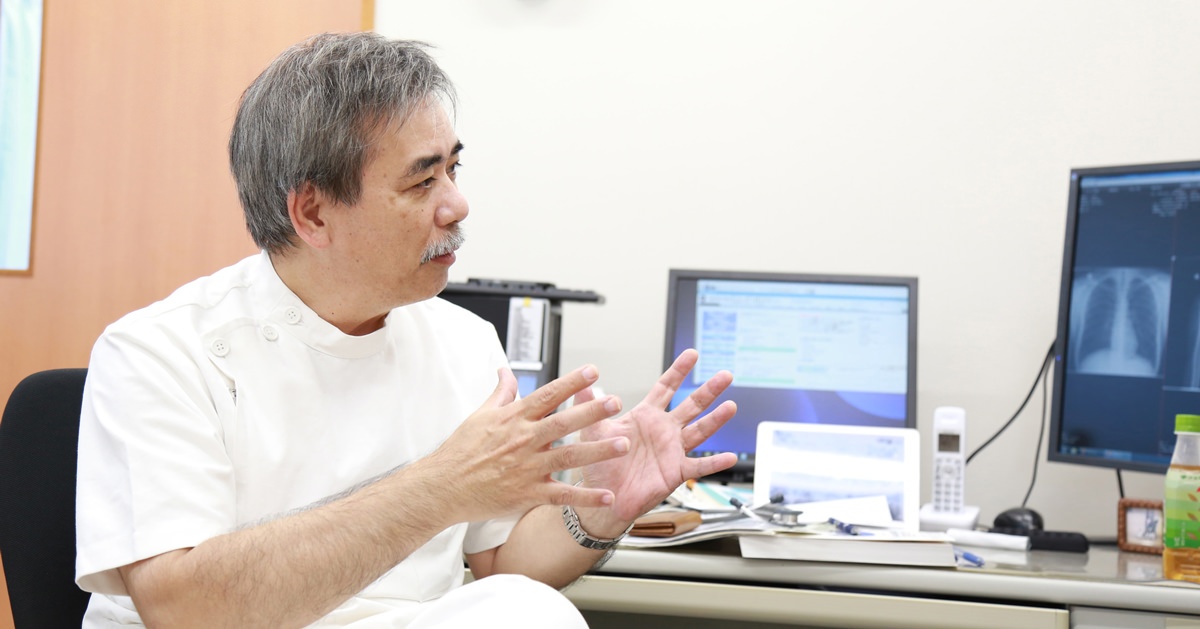 ボリビア行きの話がなくなり、研修の場は、全国的に忙しいことで有名な沖縄県立中部病院でした。中部病院では「君たちは日本一忙しい病院にきたんだ。」と言われ、大変厳しい環境のなかでの研修がスタート。しかし、この病院は救急医療を担う地域の基幹病院でしたので、ここで救急医療をしっかり勉強できたのは非常に良い経験だったと思います。
ボリビア行きの話がなくなり、研修の場は、全国的に忙しいことで有名な沖縄県立中部病院でした。中部病院では「君たちは日本一忙しい病院にきたんだ。」と言われ、大変厳しい環境のなかでの研修がスタート。しかし、この病院は救急医療を担う地域の基幹病院でしたので、ここで救急医療をしっかり勉強できたのは非常に良い経験だったと思います。
2年間、慌しく働いていましたが、患者さんに「先生たちはいつ寝るのですか?」と言われると医師として仕事をしている実感が湧いたことを良くも悪くも忘れられません。
そして2年間の研修を終えると、宮古島と石垣島の間に位置する多良間島へ赴任することが決まりました。
この多良間島への赴任が私の離島医療への道の第一歩です。
多良間に来て一番びっくりしたのは、小さな子どもからお年寄りまで、私のことをかけがえのない存在として扱ってくれたということです。大きな病院での研修中は「私は多くの集団のなかの一人でしかない」と思ってしまうこともありましたが、ここで初めて医師という職業は社会的で、やりがいがあるものだと感じました。

多良間島に来て しばらくして気がついたのは、多良間島のみなさんは、とにかくよくお酒を飲むということです。私が多良間島に来る頃にはちょうどフェリーが開通したばかりで、沖縄本島から大量のお酒を運ぶことができるようになっていました。島の住民は若者からお年寄りまでほぼ毎日のようにお酒を飲んでいたのです。あまりにもお酒の消費量が多く、健康にも良くないと感じた私は、島の住民がお酒以外にも夢中になれることはないだろうかと、ギタークラブを結成しました。島の青年や学校の先生など10名ほどで集まり、多良間小学校のリコーダークラブと合同合奏を行うなど、一生懸命取り組みました。その他にも島の住民の飲酒量を減らすために、夜10時になるとサイレンを鳴らすという取り組みを実行。これは「他所の家でお酒を飲んでいる人は帰りましょう」という合図で、付き合いがあるから自宅へ帰りにくいと感じている方に、このサイレンをきっかけに帰宅を促したのです。
このように多良間島では、診療所で患者さんを診療するだけでなく、身近なことを通して少しでも健康的に生活できるような取り組みを常に考えるようにしていました。

 多良間島での勤務を終えると、渡嘉敷島へ行くことになりました。渡嘉敷島の人口は700人ほどですが、観光シーズンの夏場になると約3倍になります。観光でいらっしゃった方々の診療を行うたびに住人の一人として思うのは「わざわざ渡嘉敷を選んで観光に来てくれたのに、具合が悪くなってしまってかわいそうだな」ということ。診療所の医師として観光客の方々に何かできないだろうかと考えた私は、夜間など診療時間外にも診療を行うようにしていました。観光客の方には、せっかく渡嘉敷に来てくれたのだから渡嘉敷を十分に堪能してほしい、診療時間内に診療所に来るのが原則ですが、それが難しい場合にもできる限り対応しようと思ったのです。
多良間島での勤務を終えると、渡嘉敷島へ行くことになりました。渡嘉敷島の人口は700人ほどですが、観光シーズンの夏場になると約3倍になります。観光でいらっしゃった方々の診療を行うたびに住人の一人として思うのは「わざわざ渡嘉敷を選んで観光に来てくれたのに、具合が悪くなってしまってかわいそうだな」ということ。診療所の医師として観光客の方々に何かできないだろうかと考えた私は、夜間など診療時間外にも診療を行うようにしていました。観光客の方には、せっかく渡嘉敷に来てくれたのだから渡嘉敷を十分に堪能してほしい、診療時間内に診療所に来るのが原則ですが、それが難しい場合にもできる限り対応しようと思ったのです。
さらに、渡嘉敷島で私が問題だと感じたのは、海で溺れてしまう方に適切な処置ができていないということでした。
「渡嘉敷島のビーチを日本一安全なビーチにしたい!」
大それた目標ですが、住民の半数が心肺蘇生法を習得できれば不可能ではないと考えていました。残念ながら赴任期間中に半数という目標は達成できませんでしたが、住民のみなさんに心肺蘇生法を教える私の姿をみた後輩が意志を紡いでくれたのです。今では、心肺蘇生法を広める団体「命どぅ宝プロジェクト」として規模が拡大。地域医療振興協会の公益事業としてバックアップするほど大きな輪となりました。私が蒔いた小さな種が花開く。取り組んで良かったなと本当に嬉しく思っています。
離島での義務年限を終え、再び沖縄県立中部病院に戻りました。当時は後輩が赴任する病院がなくなるということで、離島勤務後は県をやめて医師として働くことが一般的でした。しかし、離島医療を経験した人間が、離島義務の後、全く関係のない医療に身を投じてしまうと、後輩から見れば、「結局、義務だからやっているのか」と映ってしまいます。地域医療にやりがいを感じていた私にはどうしてもそれは「良くないこと」に思えたのです。幸いにも県立中部病院には残れることになって、そこから離島へ赴任していく若者のサポートを開始しました。
県立中部病院と離島をつなぐための仕組みづくりに奔走。沖縄本島から離島にどういう支援ができるか。さまざまな方策を試行錯誤しながら、インターネットが普及し始めた平成7年についに大きな成果をあげることができました。総務省と厚生労働省の補助金をもとに、全16の離島と中部病院にネットワークを構築することができたのです。これは今でも続いており、少なからず離島医療に貢献できたのかなと自負できる仕事です。
離島医療に二十年以上携わってきましたが、まだまだ十分な体制が整っているとはいえません。私が理想とするのは役場と住民、そして医療人がそれぞれ自覚を持ち、三位一体となることです。限りある資源を最大限に活用して、継続的に安定的な医療を行い続ける。まだまだ志は半ばですが、さまざまな取り組みを経て、着実に近づいていると実感しています。
2017年現在、私は竹富町立黒島診療所で働いています。離島医療に携わる医師としてのやりがいは昔と変わらず、住民のみなさんに安心・安全を届けることにほかなりません。「わったー島の先生」という信頼をいただけるようになるのは一朝一夕ではいきませんが、行政や住民と一体になり、積み重なる課題を解決していくのは医師としての人生を懸けるに値する仕事だと思っています。
※1 わったー・・・方言で「私たちの」という意味。
